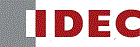病院でのバーコードの活用の現状と今後
医薬品バーコード表示の進捗
医療分野に於けるバーコードの活用に関して、2016年8月に厚生労働省からバーコード表示について義務化の改正通知が出され、2021年4月からバーコード表示の義務化はトレーサビリティに必要不可欠な薬の有効期限、ロット番号または製造番号のバーコード表示化の対象範囲が拡大されています。
医療用医薬品のバーコード表示の対象
| 医療用医薬品の種類 |
調剤包装単位 |
販売包装単位 |
元梱包包装単位 |
|||||||
|
商品
コード
|
有効
期限
|
製造番号
又は
製造記号
|
商品
コード
|
有効
期限
|
製造番号
又は
製造記号
|
商品
コード
|
有効
期限
|
数量 |
製造番号
又は
製造記号
|
|
| 特定生物由来製品 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 生物由来製品 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 注射薬 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 内用薬 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 外用薬 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
必須表示項目:◎ (◎は実施期限2021年4月(特段の事情があるものは2023年4月))
任意表示項目:○
薬の有効期限、ロット番号または製造番号のバーコード表示化に関しては、 以前は生物由来関連の製品に限定されていましたが、注射薬、内用薬、外用薬を含めた全てに関して、アンプル、錠剤シート等が入っている化粧箱(販売包装単位)とその化粧箱が入っている段ボールケース(元梱包単位)が対象となりました。
生物由来などの製品を除いて、化粧箱から出された状態の中身のアンプルや錠剤シートなどはまだ義務化されていませんが、これだけでも流通過程でのトレーサビリティが格段に取れるようになることで医療安全の大幅な促進に繋がると思われます。
現在のバーコードの表示の義務化はどうなっているのか? 製品を特定する商品バーコードに関しては2016年7月までに化粧箱だけでなく、その中身のアンプルや錠剤シートなど全てに義務化が実施されました。これにより医療現場で取り扱うに医薬品の全てに商品が特定可能なバーコード表示がされ、バーコード活用の基盤整備が出来ています。
医療現場でのバーコード活用内容
医療現場においてバーコードとは新しいコンセプトではありません。ご家族や親しい人が入院をされ、病院にお見舞いに行かれた方ならお気づきの方もいらっしゃると思いますが、医療の安全のためにバーコードが病院内のあらゆるところで多く使われています。
病院で活用されている場合、よく見かけるのは三点認証と呼ばれているものです:
点滴など投薬の際…
• 患者のリストバンドのバーコード
• 薬剤のバーコード
• 看護師さんのバーコード
の3点を読取り照合して、チェック完了後にのみ投薬を行うことです。この三点認証を行うことには主に3つの利点が考えられます:
• 患者の安全確保
• 看護師への安心感
• 病院での医療履歴保存(誰がいつどの薬を誰に投与)
もちろん患者が直接目にしないところでも処方箋に従い、用意した輸液や注射剤などのバーコードを読取り事前チェックを行っています。
上記三点認証の経験がある方、私みたいな業界の人間などは医療現場でバーコードの活用は当たり前だと思いがちかもしれません。
実はバーコードの活用は絶対的ではございません。
病院でのバーコード活用の普及状況は?
バーコードの導入が進んでいるは主に公的機関の病院や大学病院などであり、私自身が入院した400床規模の民間病院ではバーコードは使われていませんでした。
その意外さに興味が湧き、更に街の開業医ではどうなのかと深入り確認!
開業医の病院で医療事務に係る知人に聞いてみましたが、バーコードの読取りなんて全くしていないとの事でした。
なぜ使われていないのか?
一般開業医の診療所では入院患者に対する投薬もなく、診療行為で注射薬や外用薬などを使用する機会もそれほど多くないので、投資とメリットの差に問題があるからと想像しますが、実はバーコードの導入に当たって開業医だろうと民間病院だろうとどんな病院でも感じられる大きなメリットが1つあるのです。
財政負担軽減の解決策のジェネリック医薬品
そのメリットとは?広まるジェネリック医薬品に係わる問題です。
政府が高まる医療費の財政負担軽減のために2020年9月までジェネリック医薬品の使用割合を80%として促進策を検討すると言う閣議決定してジェネリック薬の普及を進めました。
その結果、ジェネリック医薬品の使用割合は年々大幅に上昇しています。
そこに潜む問題:総合病院の先生のお話では、ジェネリック医薬品は先発品の1つあたりいくつものメーカーから出されており、いくつもの異なる薬品名が存在しているため、とてもジェネリック医薬品の全ての名前を覚えることはできないということです。
このため、患者さんが他の病院で出された薬を持参して薬の飲み合わせの問題などを聞かれてもとても対応しきれないとおっしゃっていました。
その解決策としてその先生が期待されているのがバーコードです。錠剤シートのバーコードを読み取ることによりその薬の先発薬などの情報を簡単にアクセスする事ができるようになるのではないかという話をして頂きました。
その通りなのです。
その実現に必要な内用薬の錠剤シートに対して商品コードのバーコードの表示が義務化されているのですが、錠剤シートは薬局または使用時に患者が自ら切り離す場合があるので印刷箇所をどうすべきかとの課題がまだ少し残っています。
お薬手帳のメリット
ここで余談になりますが、お薬手帳にはジェネリック薬品が調剤された場合にも先発薬の名称も記載されます。実は患者がお薬手帳を必ず持って病院へ通っていれば上記のジェネリック問題は解消されるのです。しかし、お薬手帳は持ち運びに慣れていなく、急に体調が悪くなったりすると忘れがちですよね?
重要なポイント:実はお薬手帳を持参しないと薬局で支払う金額が高くなるのです。
2016年4月の法律改正以前は、お薬手帳を持参すると却って支払い金額が高くなると言う実情があり、お薬手帳が活用されない要因の1つでした。
それで医療関係者の人でもお薬手帳を持参した方が高くなると思っておられる方も多かったのですが、実のところは、改正以後は過去6ヶ月以内に調剤して貰った調剤薬局にお薬手帳を持参して行くと「薬剤服用歴管理指導料」は380円ですが、それ以外の場合は500円になります。
つまり3割負担で40円の差額ですが、過去6ヶ月以内に調剤して貰った調剤薬局に行っても、お薬手帳を持参しないと高く支払う事になります。たとえ自己負担は小さくても、税金投入されている保険医療費からの費用負担も発生してしまいます。
つい持参を忘れがちなお薬手帳ですが、電子化されてスマホアプリがあるようなので、皆さんのご家族を含めた健康管理に活用されてはいかがでしょうか。
活用イメージはどうなっているかと言うと
|
[ 薬局(薬剤師・医療関係者) ]
|
⇒ |
[ 患 者 ]
|
|
① QRコードの発行により
データを引渡し
|
②QRコードを読み込みして
データをアプリに取込む
|
|
| ⇑ | ⇓ | |
|
④ 患者がワンタイムパスワードを
発行して 閲覧許可を出すことに
より薬局などでサーバー上のデ
ータの閲覧が可能
|
③患者がアプリ上でデータを
サーバーへ預ける操作を行う
|
|
| [ データセンター (サーバー) ] |
||
しかし、お薬手帳が電子化されたと言っても上記の手順で広く活用できるようになるには、下記の様な課題もあり、まだまだ時間を要すると思います。
・電子機器の普及率や取扱い能力の問題
・スマホアプリのデータを薬剤師、医療関係者に見せにくい
(スマホ画面を見せる or データの閲覧許可を出してPC上で閲覧をする)
やはり先程ご紹介した先生が期待されていたようなジェネリック医薬品に係わる問題の解決策となる医薬品バーコードの読み取りに関して、医療機関が容易にシステム導入できるような環境整備も必要と思います。
トレーサビリティの推進にも重要な手段として更に今後もバーコードの活用が広まる事と思います。